20世紀を編集する/アメリカの世紀を超えて
イベントーク Part9 記録誌
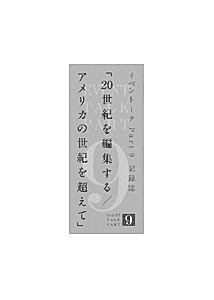
- 編集/越後谷卓司
- 発行/愛知芸術文化センター
企画事業実行委員会 - 企画/愛知県文化情報センター
- 助成/財団法人地域創造
「地域の芸術環境づくり支援事業」 - 発行所/愛知芸術文化センター
〒461-8525
愛知県名古屋市東区東桜1-13-2
Tel.052-971-5511 - 発行日/2001年3月19日
- ISBN(美術館パンフレット仕様に
つき未登録) - 定価/本体価格1500円
(直接販売につき、取り扱い書店限定)
~本書より関係部分のみ抜粋~
「アヴァンギャルドとスラップスティック-アメリカ実験映画の黎明」
越後谷卓司
アメリカの実験映画について語る時、暗黙のうちにそれは第二次世界大戦以降の時期を指している。それ以前の、1920年代にピークを迎えた戦前期は、アヴァンギャルド芸術の全盛期であり、その中心地はヨーロッパであった。実際、この時代の実験映画は、アヴァンギャルド映画(前衛映画)と呼ばれるのが一般的である。1950~70年代に興隆したアメリカ実験映画は、当時、一般的にアンダーグランド映画と呼称され、アヴァンギャルドはその前史的に位置づけられていた。この歴史認識は、今日も大きく変わるものではないし、1920年代が、アメリカ実験映画において前史的な位置に留まるという見方は自然といえる。
この時期に活躍した監督で、アメリカ実験映画と少なからぬ関わりを持つ人物の一人として、ロバート・フローリーの名前を挙げることができる。1900年にパリに生まれたフランス人で、フランスではロベール・フローレイと呼ばれる。ハリウッドとヨーロッパを行き来し活躍した人物で、後にマルクス兄弟の劇映画デビュー作『ココナッツ』(1929年)や、フランス初の本格的トーキー映画『道は楽し』(1929年)を監督、チャップリンの『殺人狂時代』(1947年)には演出補佐として手腕をふるうなど、映画史に独自の足跡を残した。
彼は、こうしたキャリアを積む直前の1927~28年に、実験的な短編映画をインディペンデントな立場で数本監督している。その中の一本『ハリウッド・エキストラの生と死』(1927年)は、ハリウッドのエキストラの落ちぶれ行く人生をモチーフに、スラップスティック・コメディとドイツ表現主義的な光と影を際立たせる画面造形を融合させたような表現で、ユニークな独自性を発揮しており、注目に値する作品といえる。後にオーソン・ウェルズ監督『市民ケーン』(1941年)で撮影監督として腕をふるったグレッグ・トーランド(本作品のクレジット上は、グレッグとのみ表記)が参加していることも特筆され、彼の実験的志向性が色濃く反映されている点も興味深い。実際この映画は、シェルドン・レナン著『アンダーグラウンド映画』(1969年、波多野哲朗訳、三一書房刊)に、アメリカ実験映画の黎明期に位置する作品として言及されてもいるのだ。
それでもなおこの作品には、戦後アメリカ実験映画の最大の特質である即物性といったニュアンスは希薄であり、直接的な影響関係を認め難いという点からも、直系的な祖と見るには、ためらいを覚えることも確かだ。フローリー自身がフランス出身であることもそうだが、やはりアヴァンギャルド映画の亜種として、ヨーロッパ的な文脈の中に位置づける方が自然であるように思える。アメリカにおいて実験映画は、美術がそうであるのと同じように、その本格的な台頭と活動は戦後からだといえよう。
ここで視点を変えて、実験映画という枠組みではなく、映画全般に視野を広げて、この時代を見てみるとどうだろうか。実験映画においてアメリカは後進的な位置にあったかもしれないが、一般的な映画という点では、サイレント時代から今日まで、その中心的な位置を占めるのはアメリカといえる。映画生誕こそシネマトグラフを発明したリュミエール兄弟のフランスに譲るものの、そのライバルとして既にエディソンが存在し、その後の展開においては、デヴィッド・W・グリフィスが実質的に劇映画を成立させ、さらにチャーリー・チャップリンやバスター・キートンらに代表されるスラップスティク・コメディが、映画の娯楽性とともに表現の特性(芸術性と言い換えてもいい)の先端を切り拓いていった、といえる。実際、フランスのアベル・ガンスや、ジェルメーヌ・デュラック、ロシアのセルゲイ・M・エイゼンシュテインといった、しばしばアヴァンギャルドの文脈で語られもする監督たちが、アメリカの映画を自国のそれより優れたものと認め、その代表的存在であるグリフィスに会い、あるいは学ぼうとした。
アヴァンギャルドとの関係で、さらに興味を引かれるのは、チャップリンの存在である。チャップリンといえば、今日では、至芸であるパントマイムによるコメディの詩人、哀愁とペーソスに満ちた"永遠の放浪者"という印象が大方の抱くものであろうが、最初期のマック・セネット=キーストン社作品においては、後年確立された被害者的キャラクターとしてより、むしろ加害者的な悪役として画面に登場していたことは、少なからず知られている事実である。
例えば、ヘンリー・パテ・レアマンが監督した、チャップリンの映画出演第二作である『ベニスにおけるベビーカー競争』(1914年)は、既に、山高帽にドタ靴というトレード・マークとなったおなじみの扮装で登場しているものの、キャラクター自体は非常に暴力的で、加害者的である。作品は、レースを撮影する映画カメラマンにチャップリンがちょっかいを出す、というもので、据えっぱなしのカメラが左右に緩慢にパンすることで事件を捉えるという、いいかげんとも適当ともいえるようなカメラワークなのだが、結果として不思議な、偶発的あるいは即興的なニュアンスを醸し出している。さらに映画内で撮影行為を描くという点を、自己言及的といえば、後年のジャン=リュック・ゴダールと通底する実験性を、ここに認めてもいい気さえする。
同年の作品『つらあて』は、チャップリン自身が監督していることもあってか、レース場を舞台にして起こる突発的な出来事を、即興的に作品化した観のある『~ベビーカー競争』に対し、やや構成的志向が見受けられる。しかし、だからといって『~ベビーカー競争』にくらべておとなしい作品かというと、そうではない。まず、チャップリンはこの作品で主役も演じているのだが、女装し、女優として登場してことに驚かされる。そして、単なる女装というのに留まらず、その姿はグロテスクかつ異様であり、強い異物感を見る者に抱かせる。もちろん、今日確立された彼のイメージとの落差が激しい、という側面を無視することは出来ないのだが、それ以上に強烈な悪夢的インパクトを感じさせることも確かだ。
シュルレアリストを代表格に、ヨーロッパのアヴァンギャルド系アーティストたちに、アメリカのスラップステック・コメディは、愛され、強く支持されたという。それは、今日見れば稚拙ともいえる、映画初期の未整理・未分化の表現という側面も否定できないものの、その一方で、コメディであるがゆえに偶発性や即興性を大胆に取り入れるという、まぎれもない積極性があったからではないだろうか。そしてこの点において、アヴァンギャルドとスラップステックは、地続きにあるといえはしないだろうか。
例えば、後年に監督した『巴里の屋根の下』(1930年)や『自由を我等に』(1931年)などによって、フランスを代表する監督として広く一般に知られるルネ・クレールが、初期に手掛けた短編映画『幕間』(1924年)は、アヴァンギャルド映画を代表する一本であるが、同時にスラップスティク・コメディとの接点を明示している作品でもある。
アヴァンギャルドという側面からは、画家のフランシス・ピカビアが原案と美術を、エリック・サティがオリジナル伴奏音楽を手掛け、美術家のマルセル・デュシャン、写真家のマン・レイや、ピカビア、サティらが出演するという、当時のアーティストらが大挙して参加した点で、その時代性を濃厚に反映していて、一種の金字塔的作品となっている。また表現においても、水中花のような美しい映像が、実はバレリーナの跳躍をガラスの真下から撮っているものであり(このことだけでも、不謹慎と言われておかしくないが)、さらにそれが可憐な女性ではなく、髭面の男であったことを、カッティング処理によって見せるという徹底した挑発性が、アヴァンギャルド美術運動であるダダイズムのエッセンスを体現している。
映画の終局部では、棺桶がなぜか自走し、どんどんスピードを上げてゆく。それを追って、厳かだった葬列が、徒競走のような騒ぎになってしまう。死を茶化してしまうという点で、神経を逆なでするような挑発性を示しているが、同時にこの追っかけ自体が、スラップスティック・コメディそのものである。ここに感じ取ることが出来る、ある種の不謹慎さは、初期チャップリン映画にあるそれと遠いものではなく、むしろ非常に近しく、同質のものといって差し支えない。
スラップスティックの代表的存在であるチャップリンが、アヴァンギャルドに与えたより直接的な影響としては、キュビスムの画家、フェルナン・レジェが監督したアヴァンギャルド映画『バレエ・メカニック』(1924年)が挙げられよう。この映画は、レジェ自身の絵画における、機械装置と都市のイメージという主題を、映像において展開した作品で、機械時代のメカニックなバレエといったイメージを核に、運動性や時間性を抽象的にコラージュしたものといえる。映画の中には、"シャルロ・キュビスト"と称される、キュビズム風で、いかにもレジェといった感じにデザインされたチャップリンが登場する(シャルロは、フランスにおけるチャップリンの愛称)。これなどは、はっきりとオマージュとして認められるものではないだろうか。
さらにチャップリンその人にも、アヴァンギャルドとのいくつかの接点を見出すことも可能だ。例えば、前述したロバート・フローリー監督『ハリウッド・エキストラの生と死』にチャップリンは感激し、『ハリウッド・エキストラ9413の生と死』と改題した上で、ユナイテッド・アーティスト社を通じ公開したという。これが反響を呼び、その評価によって、フローリーはパラマウント社と契約を結んだ。同社の初期トーキー作品の一本として、彼がマルクス兄弟の劇映画デビュー作『ココナッツ』を監督した経緯には、このようなエピソードがあった。また、彼が監督したフランス初の本格的トーキー映画『道は楽し』のプロデューサーが、ジャン・ルノワール監督作品の他、マン・レイ監督のアヴァンギャルド映画『ひとで』(1928年)などをプロデュースしたことで知られるピエール・ブロンベルジェであることなども、アヴァンギャルドの国際的な広がりを実感させ面白いが、こうしたフローリーの、映画史的にも興味深い、ユニークな足跡を残す契機を、チャップリンは作り出したといえる。(なおフローリーが、その後演出補佐として参加した、チャップリンの『殺人狂時代』では、それまでは良くも悪くも個人プロダクション的な作り方にあったチャップリン映画に、合理的な製作手法を導入し、作品の完成度を高めることに貢献したという。)
あるいはまた、1930年にパラマウント社との契約が成立し、ハリウッドへ渡ったエイゼンシュテインとの間で、チャップリンが個人的な親交を結んだというエピソードを、ここに加えてもいいかもしれない。ハリウッドの製作システムと折り合いがつかず、結局エイゼンシュテインの作品が完成することはなかったが、アヴァンギャルドの意外なほどの広がりを感させる、映画史的な挿話として興味を引かれよう。先のフローリーの他にも、アベル・ガンスやジャン・ルノワールらが、初期に短編のアヴァンギャルド映画を撮っていた事実を思い起こすと、サイレント時代に映画が表現としての一つの達成を遂げた1920年代は、広い意味で、映画の実験の時代だった、と言うのにふさわしい。狭義のアヴァンギャルドにおいて、アメリカは後進的位置にあったことは、認めざるを得ない事実だが、映画的実験という大きなうねりの中では、その一翼を担うというよりも、むしろ中心にあったといっても過言ではない。